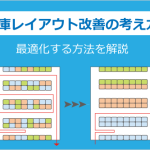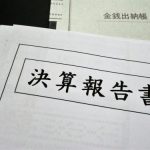物流倉庫のロケーション管理とは?メリットや導入方法を解説

「ロケーション管理って何?」と悩んでいませんか?物流業務において、倉庫内の在庫管理やピッキング作業がスムーズに行えないと、生産性の低下やミスの発生が避けられません。しかし、ロケーション管理を導入すれば、こうした問題を大幅に改善することができます。
物流倉庫におけるロケーション管理は、倉庫内作業を効率化させるために重要な取り組みの一つです。適切にロケーション管理を行うことで、在庫の正確な位置情報を把握し、作業効率を大幅に向上させることが可能になります。
そこで今回は、このロケーション管理について詳しくお話ししたいと思います。基本的な仕組みはもちろん、導入するとどんないいことがあるのか、実際にどうやって導入すればいいのかまで、分かりやすく解説していきます。この記事を読めば、皆さんの会社の物流業務を効率化するために、具体的に何をすればいいのかがはっきり見えてくるはずです。
物流の効率化に悩んでいる方、コスト削減の方法を探している方、はたまた単純に物流の最新トレンドに興味がある方など、様々な方にとって役立つ内容になっていますので、ぜひ最後までじっくりとお読みください。
目次
ロケーション管理とは
皆さん、「ロケーション管理」という言葉を聞いたことがありますか?ちょっと難しそうに聞こえるかもしれませんが、実はとてもシンプルな考え方なのです。
簡単に言えば、ロケーション管理とは、物流倉庫で「何がどこにあるか」を正確に把握できるものなのです。この管理方法を導入すると、倉庫内の仕事がスムーズに進むようになり、商品を探したり在庫を数えたりする作業の効率がグンと上がります。
物流の世界では、このロケーション管理が非常に重要視されています。なぜなら、これをうまく活用すると、仕事のスピードが上がり、ミスも減るからです。自社の倉庫をより効率的に運営したい!そう考えている方にとっては、避けて通れない取り組みの一つと言えるでしょう。
ロケーション管理の仕組み
ロケーション管理の仕組みは、主にWMS(倉庫管理システム)を用いて行われます。具体的な流れとしては、まず入庫した商品を棚に収納する際に、それぞれの商品に添付されたバーコードをハンディーターミナル(業務端末)でスキャンします。このスキャンによって商品とロケーションナンバー(保管場所)が紐づけられ、WMS上で管理されます。
例えば、新たに入庫された商品が特定の棚に収納された場合、その棚のバーコードと商品バーコードをスキャンすることで、「商品Aは棚Bの位置にある」という情報がWMSに登録されます。これにより、後に商品をピッキングする際に、WMSから出力されるピッキングリストを参照すれば、どの商品がどこにあるのかが一目瞭然となり、作業者は迷うことなく商品を見つけることができます。
また、ロケーション管理は在庫管理にも大いに役立ちます。商品の位置情報が正確に管理されているため、在庫の正確な数量を把握することができ、在庫不足や過剰在庫といった問題を未然に防ぐことができます。さらに、商品の保管場所が明確になることで、棚卸しの際の作業効率も大幅に向上し、在庫差異を減少させることが可能です。
ロケーション管理は、ピッキング作業や在庫管理の効率化だけでなく、倉庫内の作業全体を最適化するための重要な要素となります。導入することで、業務のスピードアップや精度の向上、さらにはコスト削減にもつながるため、物流倉庫の運営には欠かせないシステムと言えるでしょう。
ロケーション管理のメリット
ロケーション管理には、以下の3つの大きなメリットがあります。
ピッキングの作業効率が向上する
ロケーション管理を導入すれば、ピッキングの作業効率が飛躍的に向上します。具体的には、商品の保管場所が明確になることで、倉庫内での移動がスムーズになります。これにより、ピッキング作業にかかる時間が大幅に短縮されます。
例えば、ピッキングリストを基に商品を探し出す際、ロケーション管理が行き届いていれば、どの商品がどの棚にあるかを即座に把握できるため、無駄な動きを減らすことができます。これにより、作業時間を短縮でき、浮いた時間を他の注文分のピッキングに充てたり、作業人数を減らす(人件費の削減)ことが可能です。
さらに、効率的なピッキングが実現すれば、作業ミスも減少し、全体的な業務品質の向上にもつながります。
在庫管理の精度が上がる
在庫管理の精度が向上することも、ロケーション管理を導入する大きなメリットの一つです。商品の保管場所や在庫数が正確に管理されることで、ピッキングミスを大幅に減らすことができます。
具体的には、ロケーション管理を行うことで、在庫の数量や位置情報が常に最新の状態で管理されるため、棚卸しの際の在庫差異(帳簿上の在庫と実在庫の差異)も少なくなります。これにより、在庫不足や過剰在庫といった問題を未然に防ぐことができ、効率的な在庫管理が実現します。
また、在庫管理の精度が上がることで、注文処理の正確性も向上し、顧客からの信頼を得ることができるでしょう。
顧客満足度を高められる
さらに、ロケーション管理は自社サービスに対する顧客の満足度を高めることができます。ロケーション管理により在庫管理の精度が上がると、注文を受注してから発送するまでのリードタイムが短縮されるため、顧客の期待に応えることができます。
具体的には、商品の在庫状況をリアルタイムで把握できるため、顧客からの注文に迅速かつ正確に対応することが可能となります。これにより、商品の欠品や発送遅延といったトラブルを防ぎ、顧客の信頼を獲得することができます。
さらに、顧客からの問い合わせにも迅速に対応できるため、サービス全体の品質が向上し、リピーターの増加や新規顧客の獲得につながるでしょう。
ロケーション管理の種類
ロケーション管理には、「固定ロケーション」と「フリーロケーション」の2つの種類があります。それぞれの特徴とメリット、デメリットを詳しく見ていきましょう。
固定ロケーション
固定ロケーションは、1つの商品を決められた固定の1つの保管場所(棚やパレット)で管理する方法です。商品と保管場所が固定されていることから、シンプルな管理方法であると言えます。この方法では、特定の商品が常に同じ場所にあるため、商品の場所をすぐに特定でき、ピッキング作業がスムーズに行えます。
固定ロケーションのメリットには以下の点があります。
簡単な管理
商品の保管場所が固定されているため、場所を覚えやすく、新しいスタッフでもすぐに作業に慣れることができます。
効率的なピッキング
特定の商品の位置が常に同じなので、ピッキング作業が効率的に行えます。
一方、固定ロケーションのデメリットとしては、以下の点が挙げられます。
スペースの無駄
固定ロケーションでは、商品がなくなった場合でもその場所が空いたままになるため、倉庫内のスペースが有効活用されません。
柔軟性の欠如
商品の入れ替えが頻繁に行われる場合や、シーズンごとに異なる商品の需要が変動する場合には、固定ロケーションでは対応しにくいです。
フリーロケーション
一方、フリーロケーションは、商品を特定の位置に固定せず、倉庫内の空いているスペースに自由に収納する方法です。アパレルや雑貨など、取り扱い品目が多く、商品の入れ替えが頻繁に起きる場合に活用されることが多いです。この方法では、WMS(倉庫管理システム)を活用して、商品の位置をリアルタイムで管理します。
フリーロケーションのメリットには以下の点があります。
スペースの有効活用
商品の保管場所が固定されていないため、空いているスペースを効率的に活用できます。
柔軟性
商品の入れ替えやシーズンごとの需要変動に柔軟に対応できます。
デメリットとしては、以下の点が挙げられます。
複雑な管理
WMSを使用してリアルタイムで商品の位置を管理する必要があるため、システムの導入と運用が不可欠です。
ピッキングの難易度
商品の位置が固定されていないため、WMSの情報に頼らないとピッキング作業が難しくなることがあります。
それぞれの方法には、メリットとデメリットがあります。倉庫の規模や業務内容に合わせて、適切な方を選ぶ必要があるでしょう。例えば、小規模な倉庫や商品の入れ替えが少ない場合は固定ロケーションが適しているかもしれません。一方で、大規模な倉庫や商品の入れ替えが頻繁な場合はフリーロケーションが適しているでしょう。
ロケーション管理の導入方法
ここからは、ロケーション管理を導入するための具体的な方法(手順)を解説します。
倉庫の現状分析
ロケーション管理の導入にあたり、まずは倉庫内の現状を把握することが重要です。現状分析は、導入の第一歩として欠かせません。倉庫内の作業フロー、在庫管理の仕組み、現行の問題点などを詳細に調査し、改善点を洗い出します。この現状分析によって、導入すべきWMS(倉庫管理システム)の機能や要件を明確にすることが可能です。
作業フローの確認
現行の作業手順を見直し、どの部分がボトルネックになっているかを特定します。
在庫管理の仕組み
在庫管理の現状を評価し、誤差やミスの原因を明確にします。
問題点の洗い出し
現場スタッフからの意見を収集し、実務上の課題をリストアップします。
WMS(倉庫管理システム)の選定
現状分析の結果を踏まえて、最適なWMS(倉庫管理システム)を選定します。選定時には以下のポイントに注意しましょう。
機能の適合性
自社の基幹システムやECシステムとの連携が必要な場合、その対応可否を確認します。また、必要な機能が全て揃っているかを確認します。
サポート体制
WMSの販売元であるベンダーのサポート体制をチェックします。物流の知識が豊富で、導入後のサポートが手厚いベンダーを選ぶことが重要です。
導入コスト
システムの導入コストだけでなく、運用コストも考慮に入れ、総合的なコストパフォーマンスを評価します。
システムの設定やロケーションナンバーの発行
WMSを導入したら、次にシステムの設定を行います。具体的には以下の手順を踏みます。
商品マスタの登録
全ての商品情報をWMSに登録します。これには商品名、SKU、バーコード情報などが含まれます。
ロケーションナンバーの発行
倉庫内の全ての保管場所に対してロケーションナンバーを発行し、バーコードに印字して棚やパレットに貼り付けます。
倉庫レイアウトの最適化
ピッキングの作業効率を向上させるために、適切な導線が確保された倉庫レイアウトを決定します。商品配置の最適化を図り、作業動線を短縮します。
従業員のトレーニング
環境が整ったら、従業員をトレーニングします。トレーニング内容は以下の通りです。
ロケーション管理の仕組み
ロケーション管理の基本概念とその重要性を理解してもらいます。
WMSの操作方法
WMSの管理画面やハンディーターミナルの操作方法を詳細に教えます。入庫、出庫、ピッキングなど一連の作業フローを実践的にトレーニングします。
問題対応
システムエラーやトラブルが発生した際の対処法についても訓練します。
十分な時間をかけてトレーニングを行い、全ての従業員がロケーション管理とWMSを正しく使いこなせるようにしましょう。
テスト運用
実際の運用を想定して、入庫から出庫までの一連の流れをテストしてください。テスト運用では以下の点を確認します。
WMSの動作確認
システムが期待通りに動作するかを確認します。
不具合の修正
テスト中に発見された不具合を修正します。
改善点の洗い出し
テスト運用で見つかった改善点をリストアップし、必要な調整を行います。
テスト運用には、十分な時間をかけることが重要です。
本稼働開始
テスト運用が問題なく終了したら、本稼働を開始します。テスト運用しているとはいえ、通常の業務を行ううえで必ず課題が出てきます。PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)をもとに、継続的に改善していきましょう。
システムの保守・更新
WMSを導入した後も、システムの保守・更新を行うことが重要です。以下の点に注意します。
最新情報の反映
WMSには常に最新の情報を反映させ、在庫管理の精度を維持します。
迅速な対応
システムの障害が発生した場合は迅速に対応し、業務に支障が出ないようにします。
定期的な更新
新しい商品や倉庫内のレイアウト変更にも対応できるよう、システムの更新を定期的に行います。
定期的な保守・更新により、システムの信頼性と効率を維持し、倉庫運営の最適化を図ります。
おすすめはクラウドWMS「BEELOGi(ビーロジ)」
さて、ここまでロケーション管理やWMSについてお話ししてきましたが、「じゃあ、具体的にどのWMSを選べばいいの?」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
そこで、自信を持っておすすめしたいのが、弊社トミーズコーポレーションが提供するクラウドWMS「BEELOGi(ビーロジ)」です。
BEELOGiには、魅力的なポイントがあります。その中でも特に注目してほしい3つのポイントをご紹介します。
導入コストが安い
クラウドWMS「BEELOGi(ビーロジ)」なら、導入コストを大幅に抑えられます。クラウド型のWMSであるため、高額なインフラ構築やシステムの保守管理にかかる費用を削減することができます。また、ソフトウェアだけでなく、ハードウェア面でもコスト削減が可能です。従来の高額なハンディーターミナルに代わり、スマートフォンを活用することで初期導入コストを大幅に抑えることができます。
ハンディーターミナルは複数台必要になることが多いですが、「BEELOGi(ビーロジ)」なら、手頃な価格で必要な数を揃えることができるため、中小企業の方にも導入しやすいシステムとなっています。これにより、初期投資を抑えつつ、高機能なWMSを利用することが可能です。
ありとあらゆるシステムと連携が可能
「BEELOGi(ビーロジ)」は、マッピング(EDI編集)機能を備えており、さまざまなシステムと柔軟に連携することができます。例えば、Amazonや楽天市場といった主要なECモール、futureshopやMakeShopなどのECカート、ネクストエンジンやCROSS MALLなどの受発注一元管理システムと簡単に連携することができます。
「でも、うちの会社独自のシステムとは連携できないんじゃ…」なんて心配する必要もありません。弊社トミーズコーポレーションには社内SEが在籍しているため、自社の基幹システムとの連携などのカスタマイズも可能です。このように、さまざまなシステムとの連携が可能なため、業務の効率化を図ることができます。
物流会社ならではのサポートが受けられる
「BEELOGi(ビーロジ)」は、物流会社である弊社トミーズコーポレーションのノウハウを活かして開発されたWMSです。そのため、物流現場の実態に即した機能が豊富に搭載されています。導入後のサポートも充実しており、トラブルや問題が発生した場合でも迅速に対応いたしますので、ご安心いただけます。
さらに、「BEELOGi(ビーロジ)」の運営支援だけでなく、29年の物流実績を基にした「物流コンサルティングサービス」も提供しております。お客様の物流課題を包括的にサポートし、最適なソリューションを提案することが可能です。もし「自社で物流を改善するよりも、アウトソーシングした方がいいかな?」と思った時も、私たちにご相談ください。物流のアウトソーシングサービスも行っていますので、お客様にとってベストな選択をご提案できます。
まとめ
ここまでロケーション管理について詳しくお話ししてきましたが、いかがでしたでしょうか?
ここで改めて、今回お伝えしたことをおさらいしてみましょう。
簡単に言えば、ロケーション管理とは、物流倉庫で「何がどこにあるか」を正確に把握できるものなのです。これを導入すると、倉庫内の作業がスムーズになり、生産性がグンと上がります。そして、コストダウンにもつながります。
自社物流に課題を感じられている場合は、一度弊社トミーズコーポレーションにお気軽にご相談ください。私たちトミーズコーポレーションは、まさにそういった悩みを解決するプロフェッショナル集団です。
私たちには長年の経験と、数々の現場で培ってきたノウハウがあります。その知識と経験を活かして、お客様の物流の課題を徹底的に分析し、最適な解決策をご提案します。
物流に関する悩み、どんな小さなことでも構いません。ぜひ、私たちトミーズコーポレーションにご相談ください。きっと、お客様にぴったりの解決策が見つかるはずです。
物流のことならトミーズコーポレーションにお任せ