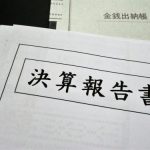物流現場の問題点と改善・効率化について

物流現場の効率化で成果を出すポイントは、倉庫内の作業だけを改善することではありません。
入荷 → 保管 → ピッキング → 梱包 → 出荷 → 配送までを、ひとつの流れとして見直し、全体最適にすることが重要です。
近年はECの拡大で出荷量が増え、現場では配送遅延・人手不足・コスト増といった課題が起きやすくなっています。
その結果、「忙しいのにミスが増える」「残業が増えるのに利益が残らない」など、負荷だけが積み上がる状態になりがちです。
本記事では、物流現場でよく起きる問題点を整理し、在庫の見える化、作業の標準化、物量の平準化を軸に、実務で使える改善策を解説します。
具体例として、ルート最適化(AIの活用を含む)や共同配送、配送条件の見直しなども取り上げます。
改善は、「見える化 → 標準化 → 平準化」の順番で進めるのが基本です。
この順序で対策を積み上げることで、コスト削減と顧客満足の向上を両立しやすくなります。
現場のムダを減らし、生産性を上げるためのヒントとしてご活用ください。
目次
物流現場のよくある問題点
物流効率化の第一歩は、「どこで遅れ・ムダ・手戻りが起きているか」を正確に把握することです。
ECの拡大やニーズの多様化で物量が増えるほど、従来の運用(人の勘・手作業・場当たり対応)では限界が来やすく、遅延やミスが表面化します。
ここでは現場で起きやすい課題を、原因と影響がすぐ分かる形で整理します。
配送業務における問題点
配送遅延リスクの増加
- 原因:出荷量の増大・繁忙期の注文集中に対して、人員配置や締め時刻が固定のまま
- 影響:顧客満足の低下/返品・再配達の増加/問い合わせ対応が増え、現場コストも増える
配送ルートの効率不足
- 原因:配達順・立ち寄り条件が最適化されていない(「いつもの順番」になっている)
- 影響:走行距離や待機時間が増える/燃料と時間がムダになる/車両稼働とドライバー生産性が落ちる
配送コストの増加
- 原因:燃料費・維持費・人件費の上昇に加え、積載率が低い/共同配送が使えていない
- 影響:利益率が圧迫される/サービス品質・価格体系の見直しを迫られる
倉庫内の在庫管理と連携の問題
在庫の過不足(過剰在庫・欠品)
- 原因:需要予測のズレ/入出庫タイミングの不一致/実在庫とシステム在庫が合っていない
- 影響:過剰在庫:保管費が増える・滞留する/欠品:販売機会を失う
※現場では「数は合っているはずなのに、棚にない(場所が分からない)」が発生源になるケースが多いです。
リアルタイムな在庫共有ができていない
- 原因:在庫更新が遅い/拠点間・部門間で同じ情報を見られない
- 影響:販売・他拠点との連携が崩れる/保管場所の特定に時間がかかり、出荷スピードが落ちる
荷主や他企業との調整における問題
配送先・スケジュール調整に時間がかかる
- 原因:共同配送や荷物配分の調整が増える/荷主ごとの要望に個別対応している
- 影響:繁忙期ほど組み換えが複雑化し、配送全体に遅れが波及しやすい
異なるシステムと連携できていない
- 原因:荷主・協力会社とデータ連携がなく、手動確認(メール・Excel・電話)が多い
- 影響:情報共有に時間がかかる/データの不整合が起きる/作業者の負担が増える
人手不足と環境負荷に関する問題
慢性的な人手不足と現場負担の増加
- 原因:ドライバー・倉庫作業員の採用難/業務が属人化している
- 影響:長時間労働 → 疲労 → ミス増加 → 離職 → さらに人が減る、という悪循環になりやすい
環境負荷の増加(CO₂・廃棄物)
- 原因:積載率が低い走行/再配達が多い/梱包資材のムダが出る
- 影響:コスト増だけでなく、企業のサステナビリティ評価にも影響する
物流の課題は単体ではなく、連鎖します。
まずは「どこで遅れ・ムダが生まれているか」を可視化し、影響が大きい箇所から優先的に手を打つことが効果的です。
問題点の改善策
物流の効率化は、「部分最適」ではなく「全体最適」で進めるほど成果が出やすくなります。
たとえば「ピッキングを速くしたのに、出荷締めに間に合わない」「人を増やしたのにミスが減らない」などは、工程同士がつながっていない典型例です。
改善は、次の順番で段階的に進めるのが基本です。
見える化 → 標準化 → 平準化 → 最適配置 → 自動化
- 見える化:遅れ・ムダ・手戻りの発生箇所を数字で把握する
- 標準化:人によるバラつきを減らし、同じ品質で回せる状態にする
- 平準化:繁忙と閑散の差をならし、波に強い体制を作る
- 最適配置:人・モノ・場所・時間の配置を最も効率の良い形にする
- 自動化:標準化できた作業から、機械・システムに置き換える
配送業務における改善策
配送ルートの最適化
配送ルートは「いつもの順番」ではなく、その日の条件で組み直すことでムダが減ります。
システムを活用し、渋滞・時間指定・立ち寄り条件などを加味して日々更新し、配送実績で見直すのが有効です。
- 狙い:走行距離・待機時間を減らす
- 効果:燃料と作業時間を同時に圧縮しやすい
※「AI」と言っても、まずはルートをデータで組み直せる状態(住所・時間指定・積載条件が整理されている状態)が前提になります。
積載率を上げて配送回数を減らす(共同配送・便の組み替え)
積載率が低いまま走るほど、配送コストは上がります。
複数荷主の荷物をまとめる共同配送は、積載率を高め、配送回数を削減する代表的な方法です。
- やること:曜日・時間帯ごとの積載状況を把握する
- 打ち手:積み合わせ/出発時間の調整/便の再設計
- 効果:コスト効率の改善(燃料・人件費・車両稼働のムダ削減)
配送進捗のリアルタイム管理
配送追跡をリアルタイム化すると、「今どこ?いつ届く?」の問い合わせを減らしやすくなります。
顧客が自分で追跡できる状態を作ることで、CS負荷が下がり、顧客満足にもつながります。
- 顧客側のメリット:到着見込みが分かり不安が減る
- 現場側のメリット:遅延・事故・再配達などのトラブルに早く気づける
- 効果:対応のスピードが上がり、全体が回りやすくなる
在庫管理と情報共有の改善策
在庫の見える化(バーコード)と自動更新
在庫の精度を上げるには、まず「実在庫」と「システム在庫」を一致させることが重要です。
バーコードで入出庫・移動を記録し、在庫数と保管場所をリアルタイムで更新できる仕組みにすると、誤出荷や欠品、探す時間を減らしやすくなります。
- 狙い:「あるはずなのに見つからない」を潰す
- 効果:作業精度アップ/部門連携がスムーズになる
需要予測に基づく在庫補充(欠品と過剰在庫の両方を減らす)
過剰在庫と欠品は、どちらもコストです。
過去の販売実績や市場動向を使って需要の波を読み、季節変動やセール時の急増を見込んだ補充計画を立てることで、
保管コストの抑制と欠品防止を両立しやすくなります。
- やること:SKUごとに「安全在庫」「補充点」「リードタイム」を見直す
- 効果:滞留在庫の削減/販売機会ロスの抑制
在庫情報の一元化とリアルタイム共有(拠点・チャネルが多いほど効く)
拠点が複数、販売チャネルが複数あるほど、在庫は分断されやすくなります。
在庫情報を一元管理し、リアルタイムで共有できる状態を作ると、拠点間移送や調達判断が速くなり、販売機会の損失を防ぎやすくなります。
- 狙い:「どこに在庫があるか」を一瞬で分かる状態にする
- 効果:出荷スピード向上/欠品の未然防止
荷主や他企業との調整における改善策
共同配送スケジュールの最適化(条件の共通化でムダを減らす)
共同配送を安定稼働させるには、締め時刻や納品条件を可能な範囲で揃え、ルートを共有できる状態にすることがポイントです。
急な変更を減らし、共同便を一定のリズムで回すことで、配送コストの平準化(波を小さくする)につながります。
- やること:「変えられる条件」と「変えられない条件」を整理して合意形成する
- 効果:調整工数の削減/便の稼働率向上
システム連携(API等)によるデータ共有の自動化
荷主との情報共有がメールやExcel中心だと、どうしても遅れとミスが発生します。
APIなどでシステム連携し、出荷情報や在庫データを自動共有できるようにすると、手動入力が減り、ヒューマンエラーを抑えながら処理スピードを上げやすくなります。
- 狙い:二重入力・転記・確認作業をなくす
- 効果:情報の一貫性が保たれ、全体の処理が速くなる
人手不足と環境負荷への対応策
自動化は「標準化できた作業」から入れる
ピッキング支援、仕分け機、AGV(無人搬送車)などの導入は有効ですが、いきなり大規模に入れるより、定型でブレない作業から段階導入する方が失敗しにくいです。
機械に任せることで、作業者は例外処理や品質確認など、人がやるべき業務に集中できます。
- 狙い:身体負荷・単純作業を減らす
- 効果:省人化+ミス削減+処理能力アップ
労働環境の改善と教育(属人化を無くす)
効率化は「スピード」だけでは定着しません。
手順の標準化と教育体制(研修・OJT・チェックリスト)を整えることで、誰が入っても同じ品質で回せる状態に近づきます。
- やること:作業手順の明文化/スキル段階表/適切な休憩設計
- 効果:ミス削減/負担軽減/離職の抑制につながりやすい
環境負荷を抑える「エコ物流」(コストにも効く)
環境対応はコスト増に見えますが、実際はムダ削減とセットで進めると効果が出ます。
積載率アップ・共同配送で走行距離を減らし、低燃費車やEVへの切り替えを計画的に進めることが基本です。
さらに、過剰包装の見直しや再利用可能な梱包材の採用は、廃棄物削減にもつながります。
- 狙い:CO₂と廃棄物を継続的に減らす
- 効果:燃料・資材のムダ削減/企業評価(サステナビリティ)にも寄与
これらの施策は、「見える化」から順に積み上げることで、現場に定着しやすくなります。
まずは小さく始めて成果を作り、その実績をもとに次のステップ(最適配置・自動化)へ進めるのが現実的です。
物流現場を効率化するためには
物流の効率化は、倉庫や配送の一部だけを改善しても成果が頭打ちになりがちです。
配送・在庫・人員・環境・テクノロジーの5要素をつなげて考えることで、コスト削減とサービス品質の向上を同時に狙いやすくなります。
ここでは、現場で実行しやすい形に整理して、具体策をまとめます。
配送の効率化を図る
AIによるルート最適化
ルートは固定せず、その日の条件で組み直す方がムダが減ります。
交通渋滞・時間指定・立ち寄り条件などを考慮して最短(または最適)経路を算出し、日々更新できる状態にすると、走行距離と燃料を抑えつつ、
配送時間の短縮や遅延リスクの低減につながります。
- 効く場面:件数が多い/時間指定が多い/渋滞影響が大きいエリア
- 前提:住所・時間指定・積載条件などのデータが整理されていること
配送拠点の再配置(近い場所から届ける)
需要が集中するエリアの近くに小型拠点を配置できると、配送距離が短くなり、リードタイム短縮とコスト低減を両立しやすくなります。
その際は、拠点間で在庫状況・出荷情報を共有できる仕組みを整えることが重要です。
- 狙い:短距離配送の比率を増やす
- 効果:遅延に強くなり、配送品質が安定しやすい
在庫管理とシステム導入を進める
ロケーション管理(バーコード/RFID)を整える
倉庫の効率は「どこに何があるか」を即答できるかで決まります。
バーコード(必要に応じてRFID)で保管場所をデジタル化し、移動・出庫の更新を徹底すると、ピッキングと商品検索が速くなり、欠品・過剰在庫のリスクも抑えやすくなります。
- 狙い:探す時間をなくす/実在庫とデータを一致させる
- 効果:誤出荷の抑制/出荷スピードの底上げ
自動倉庫・AGVで省人化(段階導入が基本)
自動倉庫やAGV(無人搬送車)は、入出庫・搬送の自動化とミス削減に効果があります。
特に規模が大きい倉庫ほど効果が出やすく、限られた人員で処理能力を上げる支援になります。
- ポイント:「標準化できた作業」から自動化する
- 効果:省人化/安全性向上/処理能力アップ
需要予測と在庫補充(欠品と過剰在庫を同時に減らす)
過去データや季節変動をもとに需要を予測し、補充の判断を仕組み化すると、余剰在庫と欠品の両方を減らしやすくなります。
データに基づいて在庫量を維持できると、倉庫スペースと在庫関連コストの最適化につながります。
- やること:SKU別の安全在庫/補充点/リードタイムを見直す
- 効果:保管費の抑制/販売機会ロスの抑制
コスト削減と環境配慮を両立する
積載率の向上と共同配送
積載率が上がるほど、配送コストは下がりやすくなります。
共同配送を推進して便数を減らすと、燃料費・人件費を抑えながら、CO₂排出量の低減にもつながります。
- 狙い:「空気を運ぶ」状態を減らす
- 効果:コストと環境対応を同時に前進できる
環境配慮型の梱包材・エコ包装
再利用可能な資材や再生素材を採用し、過剰包装を見直すことで廃棄物削減が図れます。
エコ包装は環境負荷の低減だけでなく、企業の信頼やブランド価値にも影響します。
燃費効率の高い車両・EVへの計画的な切り替え
低燃費車両やEVへの移行は、燃料コストと環境負荷の両方に効く対策です。
将来の環境規制への備えにもなり、長期のコスト管理にメリットがあります。
労働力を確保し、教育体制を整える
作業手順の標準化とマニュアル整備
業務プロセスを標準化し、視覚的に分かるマニュアルを整えると、
新人が早く戦力化しやすくなります。
属人化を防ぐことは、繁忙期でも品質を安定させるために欠かせません。
- 狙い:人によるバラつきをなくす
- 効果:ミス削減/教育コストの圧縮/運用の再現性が上がる
スキルアップとモチベーション向上
定期研修、適切な評価制度、働きやすい環境づくりは、離職率の低下につながります。
結果として、安定した労働力を確保しやすくなり、現場が回る状態を作れます。
最新技術を活用した効率化
IoTによる設備・環境の監視(異常を早く見つける)
IoTで温湿度や設備稼働を常時監視できると、異常の早期検知が可能になります。
商品の品質維持と設備の安定稼働を両立しやすくなります。
AIによる需要予測と在庫最適化
AIが消費動向を多角的に分析することで、余剰在庫や欠品を抑えやすくなります。
データに基づく計画で、倉庫スペースの有効活用と在庫関連コストの削減を狙えます。
物流の効率化は、これらの施策を単発で終わらせず、組み合わせて回すことが重要です。
配送・在庫・人員・環境・テクノロジーを連動させるほど、持続的なコスト削減と品質向上に近づけます。
まとめ
物流の効率化は、納期・品質・コストを同時に改善するための土台です。
倉庫や配送の一部だけを改善するのではなく、入荷から配送までを一つの流れとして見直すことで、成果が出やすくなります。
改善は、次の順番で整えるのが基本です。
見える化 → 標準化 → 平準化 → 最適配置 → 自動化
-
配送業務の最適化:
ルートをデータで組み直し(AI活用を含む)、積載率を上げることで、走行のムダを減らし、配送遅延とコスト増を抑えやすくなります。 -
在庫管理の高度化:
ロケーション管理を徹底し、自動更新・自動化設備を段階導入することで、実在庫とデータのズレを防ぎ、過剰在庫と欠品のリスクを下げられます。 -
持続可能な物流(エコ物流)の推進:
低燃費車両・EVへの移行、梱包材の再利用や過剰包装の見直しは、コスト削減と企業価値の向上の両方に効く取り組みです。 -
人材の確保と育成:
手順の標準化、分かりやすいマニュアル整備、継続的な研修により、属人化を防ぎ、現場の生産性を安定させ、人手不足の影響を抑えやすくなります。
物流現場の改善は、単なる作業スピードの向上ではありません。
持続可能な経営と顧客満足の最大化に直結する、重要な経営課題です。
トミーズコーポレーションでは、アパレル物流をはじめ多様な業界での支援実績をもとに、現場の状況に合わせた物流改善をご提案しています。
物流現場の課題整理・改善の進め方・具体策の検討まで、まずはお気軽にご相談ください。
FAQ:物流現場の改善に関するよくある質問
物流現場の改善に関して、よく寄せられるご質問とその回答をまとめました。
Q1. 物流効率化を始めたいのですが、どこから着手すべきでしょうか?
+
Q1. 物流効率化を始めたいのですが、どこから着手すべきでしょうか?
+
まずは現場の「見える化」から着手するのがおすすめです。
作業時間、ミスの発生箇所、配送の積載率などを数値化して、どこに大きなムダや停滞があるかを特定します。
そのうえで、影響の大きい箇所から標準化(手順の統一・マニュアル化)を進めると、多額の投資をしなくても改善効果が出やすくなります。
Q2. 共同配送を導入したいのですが、他社とのスケジュール調整をスムーズに行うコツはありますか?
+
Q2. 共同配送を導入したいのですが、他社とのスケジュール調整をスムーズに行うコツはありますか?
+
コツは、締め時刻や納品条件などの「共通化」を段階的に進めることです。
まずは荷主ごとの要望を整理し、共通ルールにできる部分を増やすと、ルートや便の組み換えが楽になります。
さらに将来的に、APIなどでシステム連携し、出荷情報や予定を自動共有できる体制を作れると、調整の手間を大幅に減らせます。
Q3. AIや自動化システムの導入は高額ですが、中小規模の現場でもできる対策はありますか?
+
Q3. AIや自動化システムの導入は高額ですが、中小規模の現場でもできる対策はありますか?
+
可能です。まずは設備投資より先に、既存オペレーションの見直しによる「平準化」が効果的です。
たとえば、受注・補充・出荷のタイミングをずらして作業ピークを分散させる、回転率の高い商品を最短動線に置く(ロケーション最適化)などは低コストで実施できます。
そのうえで、ハンディターミナルの導入など費用対効果の高いところから段階的にデジタル化するのが一般的です。
Q4. 誤出荷がなかなか減りません。システム導入以外ですぐにできる対策はありますか?
+
Q4. 誤出荷がなかなか減りません。システム導入以外ですぐにできる対策はありますか?
+
まず効くのは、作業手順の「標準化」と環境整備です。
写真付きの分かりやすいマニュアルを用意し、誰が作業しても同じ精度が出る状態を作ります。
さらに、似た商品を離して配置する、棚の表示を大きくする、色分けするなどのポカヨケ(ミスを防ぐ工夫)を徹底すると、誤出荷を抑えやすくなります。